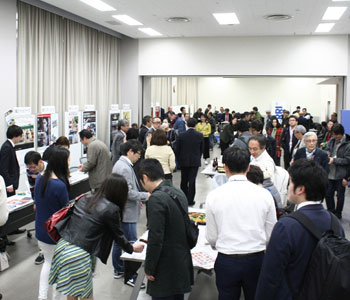数々のメガヒットアニメーション作品を手掛けてきたスタジオジブリ。
今回は特別に、スタジオジブリ・プロデューサーの鈴木敏夫さんにキネプレの森田がインタビュー。
映画の地方での宣伝についてこれまで手がけられたことや、これからの映画について、お話を伺ってきました。
※インタビューの模様は、ラジオ「鈴木敏夫のジブリ汗まみれ」でも6/2(日)23:00~放送予定です。
 |
―キネプレの森田と言います。キネプレは関西での映画情報配信をメインとしているウェブサイトです。
今回は、スタジオジブリの地方での映画宣伝の事例や、鈴木さんが取り組まれてきた宣伝の考え、またこれからの映画の形についてお話をお伺いできればと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
―まず、スタジオジブリさんは、監督をお連れして地方に行って取材を受ける、いわゆる「キャンペーン」を精力的に取り組まれている印象がありますが、そのお話を聞かせていただければ。
宮崎駿とはたとえば『もののけ姫』や『千と千尋の神隠し』の時、日本全国いろんなところ行ったんです。
各映画会社さんでは、もちろんキャンペーンというのはたしかにありました。でもそれまでは東京・名古屋・大阪・福岡、プラスアルファで札幌ぐらい。主要な都市しか行かなかったんです。
で僕は『紅の豚』の時に思ったんです。なんで主要都市だけ回るんだろう、って。だって僕らスタッフと、実際の観客が直接接するのってなかなかないでしょう。じゃあ「みんなが行かないところに行こう」と。『紅の豚』で全国18カ所、短い期間だったんだけど回ることを提案したんです。
その時、これはもう時効だから言っちゃいますけど(笑)、東宝からストップが出たんです。18カ所も回るのはダメだと。
それまでのキャンペーンって、日本全国回って遊びまくるんだろう、と思われてたの(笑)。冗談じゃない、そんなことはやめろ、と当時の営業の人に言われて、説得したんです。
―やっぱりそれは予算的なお話でしょうか。
話を聞くと、映画監督たちが日本全国回ると、やっぱ豪遊するらしい(笑)。お金ばっかり使っちゃって。たとえばある人は、あんまりキャンペーンと関係ないのに京都に行く。なんでかというと、祇園があるから(笑)。一晩の費用が数百万に達する、とかよくあったんですよ。
その点で言うと、僕や宮崎駿はすごく地味だった。いろんなもの食べたってしょうがないし、ということで質素だったんです。現地に着いてもお酒も飲まない。
その代わり、『紅の豚』の時に宮さんが言ったのが「パチンコに行こう」。そして凶悪なこと言ってきたんです。「鈴木さん、18カ所の全国のパチンコ屋を制覇しよう」と(笑)。「全国で勝ったらこの映画はヒットする」とか言っちゃって(笑)。
―全国それぞれの都市で勝つ必要があったんですね(笑)。
全部で勝たないとこの映画のヒットは無理だろう、と言って、パチンコ屋を探したんです。最初はたしか青森からスタート。そのパチンコ屋はあんまり人がいなくて、宮さんがためらったりしたんだけど、「えいや」とばかりにやり始めたんです。でも出ない(笑)。一緒に行った日本テレビの奥田誠治さんらも負ける。
でも宮崎駿は、自分で言いだしただけあって、心構えが違う(笑)。真剣にやるわけです。僕だって負けてられないから真剣にやる。結局いくら使ったかはわからないけど、ついに勝ったんです。
そしてそこを皮切りに、18カ所で全勝したんです。宮さんの、勝たなきゃいけない、という意気込みはすごかったよね。
―それ以外の地方での展開についても教えてください。
現地に行ってキャンペーンって何をやるの、というと、一つはそれぞれの地方にメディアがあるでしょう。テレビや新聞、雑誌などの取材を受ける。テレビは、例えばスタジオジブリは日本テレビさんがだいたい製作委員会に入っていたから、日本テレビのネット系列局の人が頑張ってくれたわけです。
あと、その地方で試写会をやるとすると、タイアップしてくれる企業がいて、応援してくれたんです。さらに、僕らが行ったことによって、テレビで試写会をやりますよ、という告知が流れるんです。僕らも宣伝のお金はそんなに無かったんだけど、試写会の告知はお金がかからないんですよ(笑)。それはありがたかったです。
―テレビCMの代わりに無料で告知できる、というのは効果が強かったわけですね。
そしてもう一つ大事だったのは、映画館も回ったということです。映画館に行って、みんなで一緒に写真撮ったりしたわけです。
―それはシネマコンプレックス(シネコン)が広まる前の時代でしょうか。
そう。一つ一つ映画館には館主さんがいて、彼らが上映する作品を決めていた。それを回って、館主さんに挨拶するんです。そうするとそれぞれの映画館の人たちが、宣伝に前向きになってくれるわけですね。
―キャンペーンで地方の取材を受けて、地方のメディアの方のモチベーションをあげるだけでなく、上映される映画館の方のモチベーションも挙げていく、ということですね。
それはシネコン時代になってもそうで、たとえば映画館のスタッフの方全員と写真を撮ったりするんです。そうすると、あとでその事務所にその写真が飾られたりする。現地に行ってポスターやスタンディー(劇場に配布される宣伝用の立体物)にサインもしたりしましたね。
そしてもう一つ考えたことは、どこへ行くか、ということです。さっきお話した主要都市はみんなキャンペーンで行くけど、それ以外はあんまり誰も行こうとしなかったわけです。でも僕らはみんなが行かないところを選んだんです。ともすると、映画館のない街に行ったりもしました(笑)。
たとえば『紅の豚』の時もそうなんだけど、宮城県の気仙沼には映画館にはなかったけど行ったんです。皆さんが行ってないところの観客の掘り起こしは意味があると思ったんですね。
―途中では、コンビニと一緒にやる取り組みがどんどん増えてきた印象です。
それは『千と千尋の神隠し』からですね。それまではやってないんですが。
あれはですね、ローソンという会社に山崎さんという方がいて、千と千尋が始まる前に僕を訪ねてきたんです。何かなあと思ったら、いきなり「鈴木さんはコンビニが嫌いですよね」って言われた。確かに嫌いだった(笑)。いい店がいっぱいあるのにとって代わっちゃって、と思ってました。
でも山崎さんは「私はローソンとして、この千と千尋を何が何でもヒットさせたい」と言って、手帳を見せてくれたんです。「これは私が映画を観た歴史の本なんです」と。それぐらい映画が好きで、そんな人がローソンとタイアップさせてほしい、と言ってきた。それがすごかったんです。
それまではね、本当に何も知らなかったし、コンビニに偏見もあったしね。でも、コンビニには若者たちが集まる、という現象を知りました。ヒット曲もコンビニで生まれたり、山崎さんを通じていろんなことを知ったんです。ローソンの新聞、ペーパーみたいなものを、千と千尋でまるごと作りませんか、とも言われたけど、それがとんでもない部数だったんです。何百万部、という。
「コンビニではそんなことができるんだ」と思ってびっくりしたし、作って設置したら2日でなくなったと。そのときはじめて、「千と千尋ってヒットするかもしれない」と思いました。
―その時にコンビニの威力を知ったわけですね。一つのメディアになる、という。
そうですね、新しいメディアでしたね。
―ほかにも、地方の宣伝ではどういったことを取り組まれていたんでしょうか。
今はシネコンになったから、地方の館主さんと直接やり取りして、というのは無くなっちゃったんですが、今までは宣伝キャラバン、というのもやってたんです。各地方を回って、「この映画はいかがですか」と各館主さんに売っていった。それがもう意味なくなっちゃった。シネコンだと本部の判断で決まるわけだから。
そういうことの変わり目が、ちょうど『もののけ姫』の頃でした。千と千尋になるとシネコンがわっと増えた。千と千尋の頃は、本当の自由競争をやる、その唯一の時期だったんじゃないかな。だから気が付いたら日本中に千と千尋だらけになった。それがああいう数字(興行収入308億円、日本国内での映画興収歴代1位)を生み出した。
だから今もう一度ああいうことをやる、というのはもう難しいよね、と思っちゃうんです。いろんなプロデューサーが千と千尋を超えようと頑張るでしょう。ちょっとむなしいんだよね(笑)。時代時代の事情というのもあるから。
―宣伝の手法やメディアも時代によって変わってきました。
そう、やっぱり変わっちゃったんです。僕らの時は東京で発信すれば、それがおのずと日本全国に行きわたったじゃないですか。それがある時期から変わってしまう。例えばテレビだと、東京で流している番組がある。地方にはその系列のネット局があるけど、そこではもう東京の番組は流されてないんです。朝から夕方まではその地域で制作した情報番組がほとんど。東京で作ったものをみんなが観るのは、夜まで待たないといけない。そういう時代になっちゃったんです。
NHKも変わりました。昔は東京でNHKの取材を受けたら、日本全国に流されていたのが、各地方のNHKに出ないといけなくなっちゃった(笑)。そうこうしているうちに年取っちゃったから、なかなか地方に行くのが難しくなってしまいましたね。
―キャンペーンがどんどん大変になっているということですね。
そうなんです、ある意味ではね。僕らも体が元気だったらやりたいけど難しいよね。
―時代の変化についても聞かせてください。これまでは映画館に向けた作品を作って、あとでDVD・地上波へ、という流れがメインでしたが、今では最初から配信向けを想定した作品が生まれてきています。そのあたりはどうとらえられていますか。
もちろん僕らの時代は、作品は小屋(映画館)にかける、というのが最初にやってきましたね。もちろん今ではいろんな手だてが出てきたじゃないですか。作った作品をどこでいろんな人に観てもらうか、という。だからその時代時代に見合った形というのはある気はしていますけどね。
でもまだまだ映画館ですよね。配信も残念ながらまだ皆さん思ったほどはいろんな人が観ているわけじゃないし。
僕なんかは本当は配信は、1960年代の映画をやってほしいんですよね。全然無いんですよ。
―過去の名作ですね。たしかにあまり見かけないですね。
最近分かってきたんですけど、名作映画って1960年代に生まれてるんですよ。60年代に生まれた映画が、その後にリメイクされたり影響を受けたり、バリエーションでいろんなお話ができている気がします。それは日本だけじゃなくて世界で起きてきたし、映画だけじゃなくて小説や音楽もそう。60年代ってすごいんですよ。
―それ以降の作品は、そういったものにリスペクトをして作られたものということですね。
そう。ある人は「僕らはコピーの世代だ」って言ってました。そうするともっと若い人は「僕らはコピーのコピーの世代だ」って言ったり。
僕もそれなりに配信サービスに加入していろいろ観たけど、気になったのはやっぱり、60年代の映画がどこにもないということ。だから配信の会社の人に会うたびに「なんで60年代の映画やってくれないんだ」って言ってきたんです。日本のも海外のも一番面白いはずなのに。
でも最近教えてくれたのは、「許諾が大変だ」ということなんです。60年代に映画を作ってた時は、今みたいに著作権の権利の意識がなかったから、それを流すためにはスタッフだけじゃなくて出演者その他みんなの許諾が必要になってくる、それはビジネスとして割に合わない、ということだったんです。
僕はいまキネマ旬報という雑誌で、映画の連載をやっています。頼まれたときにこう言われたんです。「鈴木さん、古い映画を語ってほしい」と。どうして、と聞いたら、「語れる人がみんな死んじゃった」って言うんです(笑)。淀川長治さんはじめね。「順番でいうと、次は鈴木さんなんです」と言われて(笑)。で、自分が若いころ観ていた映画を選んでいると、おのずと60年代の作品になったんです。連載を書くために観直すと、やっぱり面白いんですね。
―映画のコピーについても伺いたいです。たとえば昨年末からは『ボヘミアン・ラプソディ』が大ヒット。クイーンについてだけでなく、だれもが共感できる思いを描いたのが一つのヒットの理由でした。今の時代、刺さる映画というと乱暴ですが、「これは自分のことだな」と言ってくれるものが強いのかなと思ってますが。
自分のため、だけじゃないというのが一つのポイントかなと思います。その時代にみんなが求めているもの、観たいと思っているものを見つけた人が結果を残せるんじゃないかなと。それって誰もわかんないわけですよ。いつも新しい時代だから。
僕らも作るときは、今何作ったらいいんだろう、というのは常に考えますよね。
―スタジオジブリさんの作品でも、いつも時代を見つめていらっしゃいますね。
それが最大のエンターテインメントだと僕は思ってるんですよね。
―そういう空気感を、作品を作っている途中でキャッチコピーやボディコピーに落とし込んでいくわけでしょうか。
それは最初から決まってるんですよ。僕は宣伝だけやってるわけじゃなくて、企画にも立ちあってるわけでしょ。だいたいその瞬間に見えてくるんですよ。それをどっかに置いとくんです。そして作品ができて宣伝しないといけない時期に生かす、ということです。
―立ち上げから作品にかかわってる鈴木さんだからできることですね。
そうですね、だからほかの作品の宣伝だけやれ、って言われたら困っちゃうんですよね(笑)。どうしたらいいかわかんないから。
―以前、鈴木さんは「プロデューサーは探偵の仕事に似ている」とおっしゃっていました。
ああ、言ってましたね。監督が何考えているか探っていく。監督はだいたい悪いやつが多いからね(笑)。どういう動機でどういう犯罪を犯すか、という(笑)。映画づくりってそれに近いですよね。それを見ているのが好きですね。
―監督がどういう意図で作っているかを明らかにしていく、ということですね。
そうですね。
つまり向こうは完全犯罪を狙っているわけでしょ(笑)。それをどう暴くか。バレたらイヤだろうしね。やっぱり腹の中では「今の時代、この映画を作りたい」という思いがあるんです。なんとなく観てほしい、なんてのはないわけです。みんな確信犯だから(笑)。
―その思いを組みとっていくということですか。
「思い」という言葉はあんまり好きじゃないんです。何を考えたか。それを暴く。取調室で「吐け」と言うみたいなもの(笑)。
『ハウルの動く城』の時は、宮崎駿に「こんなのバラされたら困る」みたいに言われました(笑)。「宣伝するな」とも言われたから、逆に中身をちゃんと言わない宣伝をしましたね。
―それがむしろ、ミステリアスというか、興味を引く結果になって動員につながった気もします。
結果的にはそうなりましたね。やっぱり映画って面白いんですよ。
鈴木敏夫さん、ありがとうございました。
当日のインタビューの様子は、TOKYO FMのラジオ「鈴木敏夫のジブリ汗まみれ」で6/2(日)23:00~放送予定です。
| 詳細情報 |
|
■サイト ・ラジオ「鈴木敏夫のジブリ汗まみれ」 |